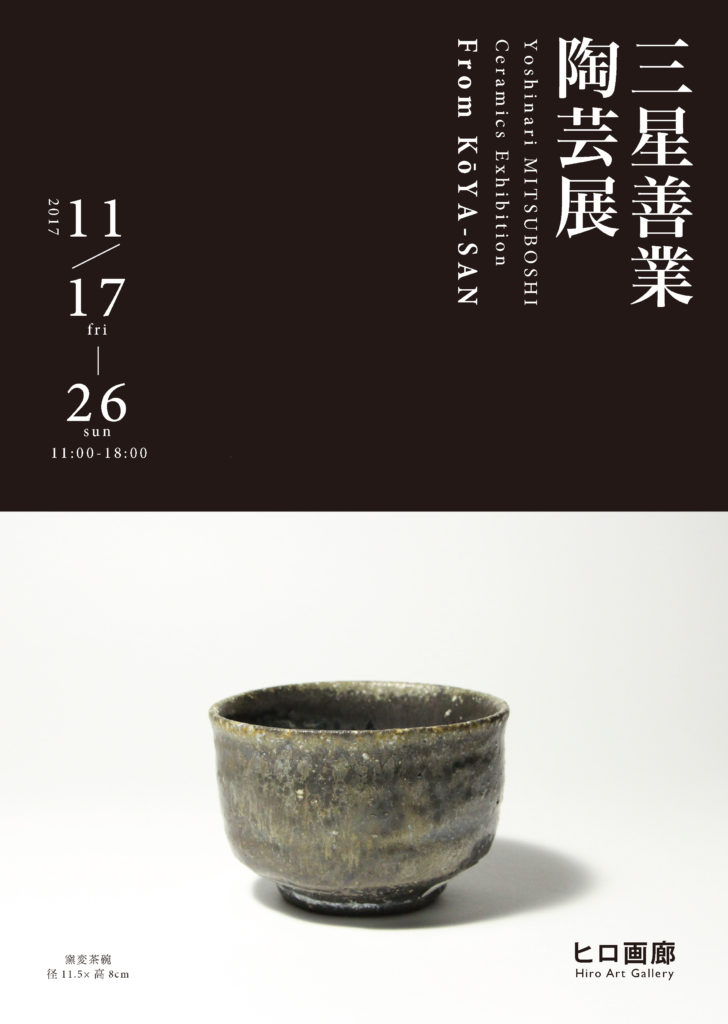「文字伝達の手段、教育の一環……色々な意見がありますが、書や篆刻というものはその人の精神性を現すものと思っています」(真鍋井蛙)
篆刻家・真鍋井蛙さんの個展に際し、真鍋さんと生前の交流があった書家・松永薫(号:白洲)の作品を展示され、真鍋さんが今なお篆刻と書の指導でかかわりのある大阪・藤井寺市の松永白洲記念館を今回訪れました。 松永白洲は、1913年(大正2年)生まれ。教育者としての仕事のかたわら地元に腰を据えた創作活動を行われました。生家は大和川のほとりで、ちょうど大和川付け替工事の基点の辺りにあり、号の「白洲」も大和川の砂を意味されます。旧家の記念館は、江戸時代に建てられ、高天井に太い梁が黒光りし、ご先祖の御典医が用いたという薬箪笥や、往診に使った駕籠が現在も保存されており、座敷の壁一面には、白洲が制作に励んだ作品が飾られています。記念館の館主で、白洲の長男である松永明さんにお話しをうかがいました。
聞き手・構成・撮影=廣畑貴之
—松永白洲記念館の成り立ちを聞かせてください。
館主 松永明 生前、父親である白洲からは「自分が亡くなったら……1回だけ遺作展をやってくれ」そのように言われていました。遺言通り、藤井寺市のパープルホール(藤井寺市立市民総合会館)を借りて展示会を行いました。遺作展はとても盛況で、なかには「(白洲先生の)16回の個展で一番良かった」という声もありました。その後、記念館の前身である白洲の家を私が64歳の時に相続しました。遺作展後に「また展示会をしてください」という声がたくさんあったこともあり、その2年後に「家を白洲記念館にして、作品を見てもらおう」という発想につながりました。私と妻(松永節子さん、右頁右下写真右から二人目)とで、誰か一緒にやってくれないかと身内に相談したところ、妹(古野英子さん、最下部写真右端)夫妻が手を挙げてくれました。そのようにして、この家を引き継ぐことで記念館は細々とスタートしました。
—真鍋さんとの出会いというのは?
松永 真鍋先生との出会いですが、この記念館の近くにある潮音寺の水野悟游さんが毎月一回十人くらいで、篆刻の会を開かれていました。そこに、真鍋先生が篆刻を教えに来られていたことがきっかけです。真鍋先生は当時30歳ぐらいだったでしょうか。そこに、父が近所だからと、 ちょくちょく顔を出していました。真鍋先生は父の話になると「白洲さんが来られたら……いつもお酒のにおいがぷんぷんで」と仰いますね(笑)。父は、自宅で一杯引っかけてから印材を持って教室に行っていたようです。

—その頃の真鍋さんは、日展の篆刻部門で初入選されて、気鋭の篆刻家として名を馳せ始める時期です。松永さん自身はそれまで、展示の仕事の経験はあったのですか。
松永 一切なかったです。転勤族のサラリーマンでしたので。記念館をスタートした当初は、ほこりを被ってしまった作品のクリーニングや書作品ごとの写真撮り、サイズ測定……1740点の作品のリストアップ等に3年かかりました。ただ、最初に話した「遺作展をやってくれ」とは別に、「週三日は必ず、家に風を通しに来てくれ」とも父からは言われていました。結果的に、記念館を始めたことで、土曜・日曜・月曜の週三日この家に風を通すことになりました。記念館をオープンして以降は、藤井寺市も観光案内パンフレットと地図に掲載してくれるなど、次第に知名度も広がっていきました。人と人とのご縁も産まれる一方で、地域の歴史が発掘された資料館としての責任も生まれてきました。
—「地域の中」という点で、近年では行政や自治体が「コンパクトシティ」の都市計画を掲げ、健康増進と医療費削減を目的に、ウォーキングやスタンプラリーのイベントが全国各地で増加しています。松永白洲記念館も近鉄(近畿日本鉄道株式会社)のイベントをはじめ、多くのコースに組み込まれています。
松永 このインタビュー直前にも「第2回河内の古民家めぐりスタンプラリー」で大阪市内から年配の方が来られました。私は一期一会のご縁を何よりも大切に、来られる方々が納得していただける様な説明を心がけています。わざわざ足を運んでくださっているのですから、ただ来てもらって終わり、ということにはしたくありません。記念館の成り立ちや大和川周辺の歴史、そういった知識を得てもらい、気持ちよく過ごしてもらえるようお迎えしたいです。そうすることで、その方が新たな方をご紹介してくださる傾向も強く感じています。昨年には、貴重な写真を新たに発見しました。
1923年(大正12年)4月、駅舎の前に大阪鉄道株式会社の重役が並んで写っています。この駅舎は現在の近鉄南大阪線の起点である大阪阿部野橋駅で、開業3日前の写真です。94年後の現在、この場所には日本で最も高いビルである「あべのハルカス」がそびえています。近鉄さんにも無い貴重な資料です。そのほか、1897年(明治30年)の河陽鉄道の工事で、イギリス・ロンドンから輸入した橋梁を大和川に架設する際の記念写真には、今では考えられませんが子供を抱いて写真に納まる職人の姿もありました。

—人口減社会に加え空き家の増加、芸術上・歴史上価値の高いものを守る文化財保護法の観点もあり、近年ではリノベーション、カフェやアートイベントでの利用など、古民家を再活用する動きが活発です。
松永 そうですね。やはり国の方針としては、古来の日本的な家屋の維持と減少に歯止めをかけたいようで、重要文化財や登録有形文化財になることで相続税などが減税される現実もあります。最初に話したように、この記念館を始めること自体そもそも考えていませんでした。たまたま相続した家があり、どう使っていこうかと親族と色々な意見を出し合って、この形に落ち着きました。ただ、自分たちにいくらバイタリティがあるといっても、今のペースでいつまでも活動出来るわけではありませんからね。私は現在80歳ですので、体に不調が出て車の運転もいつか出来なくなるかもしれません。これからの課題としては、白洲の作品は記念館で完結できますが、大阪鉄道に関する資料をはじめ、江戸後期100年間四代六人の漢方医の諸資料、その前の庄屋時代の古文書等々……そういったものをどのように後継していくか。歴史の中で人間は当然生きていますからね。「家」だけ残っていても形骸に過ぎません。今ある資料を適切な資料館や研究機関など、受け皿となる場所へバトンタッチして、自分たちのやり方で文化を継承していきたいです。
—リタイアされた多くの方が、その後趣味に没頭されたり、次の仕事を探されたり、地域活動に従事されるなど、世間との新たなかかわり方を模索されます。松永さんにとって、記念館の運営が「定年後」のライフワークであり、お父さまやご先祖と対峙する時間になったということでしょうか。
松永 ライフワークではなくて、「ここにあった芸術や文化を発掘」している心境ですね。 家族から薄々は聞いていましたが、作品を整理していくなかで大量の油絵が出てきたこともあり「父は絵描きになりたかったんだ」と確信しました。けれど「芸術で生計を立てられるのか?」と祖父から反対されて、師範学校にすすんだようです。でも、絵は描き続けていたこともあり、遺作展では若い頃の油絵作品を展示出来ましたので、少しは本望に添えたのではと思います。

—作品や建物に人とモノが行き交い、「空間が生きて」いるか、そうでないか。目には見えないですし、データとしては表れないですが、五感に響くものは確実にあるように思います。今日は記念館に入って、すがすがしい空気を私は感じました。
松永 そう言っていただけると、大変嬉しいです。三日坊主で終わらずに記念館を維持できているのは、真鍋先生はじめ周りの方々の支え、イベント時には妹婿・哲夫さんはじめ、妹・英子の「楽しい一筆」教室のメンバー50名が記念館のスタッフとして総出でお客様のおもてなしをしてくれています。これらは、本当に心強いです。教室の展示会を催したときなど、出品者は当然お知り合いをお招きされますよね。そのようなときに、自分たちの作品を批評し合ってサロン風にゆったりとされたり、すぐそばでは白洲と真鍋先生の説得力のある作品があり、鉄道資料や漢方医資料や古文書を見入られる方……そういった「人の輪」が循環していることで、地域社会の中でも存在感を示している確かな自負はあります。真鍋先生におかれては、記念館の題字(写真下)も揮毫してもらいました。書道の記念館としても、何かにつけてご指導いただいています。記念館で開催する先生の篆刻教室には、藤井寺市だけでなく富田林市、遠くは京都・奈良から習いに来られている方もいらっしゃいます。父が70歳にして近所の篆刻教室に行き、30歳の真鍋先生に教わったことがご縁となり……息子の私も先生のお人柄に魅力を感じさせて頂いております。

松永白洲記念館 Matsunaga Hakushu Memorial Museum
〒583-0003大阪府藤井寺市船橋町5-10 http://shu.no.coocan.jp 090-4306-6109 (館主 松永明) 駐車場 6台有 近鉄道明寺線・柏原南口下車 大和川を渡り徒歩6分
江戸末期に建てられた河内の民家をそのまま記念館として公開し、大和川を愛した書家松永白洲氏の奔放、多彩な作品が季節に応じて展示されています。記念館は”心ふれあうやすらぎの場”として、ご家族が公開提供されています。